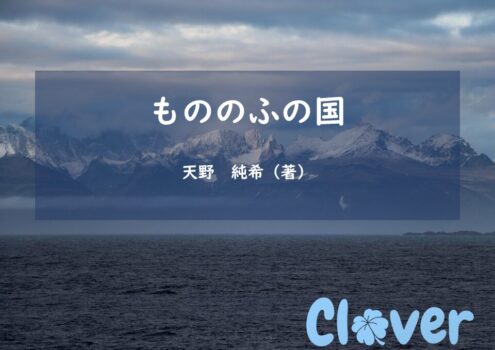久々に聞きました。「もののふ」という言葉の響き。
戦国時代は名だたる武将の名前が浮かびますよね。
この武将たちを運動会のように、山と海の2つの組にわけるとしたら、
自分の好きだった武将は海派なのか山派なのか?
螺旋プロジェクトならではの対立構造で楽しめる本でした。
目次
紹介する本の概要
| タイトル | もののふの国 |
| 著者 | 天野 純希 |
| 出版社 | 中央公論新社 |
| 出版日 | 2022/12/21 |
螺旋プロジェクト 中世・近世編
源平の戦いから戦国時代、幕末まで、およそ700年にも及ぶ武士の時代を
山族と海族のVS構想で回想できます。
源氏vs平家
信長vs明智
豊臣vs徳川
明治維新:幕府vs倒幕派
の戦いを描く歴史小説です。
どんな人にオススメ?


- 戦国時代の話が好きな人
- 天下人(信長、秀吉、家康)が出てくる物語に興味がある人
- 明治維新(西郷さん、坂本龍馬、新選組)あたりの物語が好きな人
- 螺旋プロジェクトをコンプリートしようとしている人
歴史小説のため
時代の登場人物と結末は変わることはありませんが、
螺旋プロジェクトの対立構想に掛け合わせて
仮にあの武将が海族だったら?こっちの武将は山族だったら?
とういう空想がはまって面白かったです。
所感
好きな武将は海派?山派?
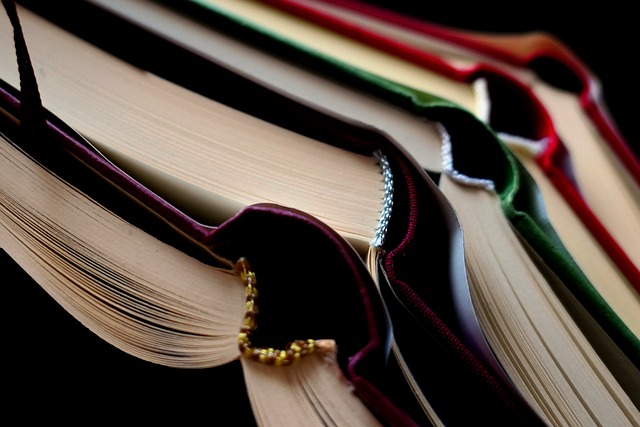
キッカケは螺旋プロジェクトで本作を知りました。
歴史をモチーフにした話は好きだけど、最近、読んでなかった気がします。
中学生の時は歴史が好きで、
源氏や戦国時代のところにはヒーロー(武将)の名前がたくさん並んでいることに
テンションが上がっていたことを懐かしく思います。
戦国時代、熱いですよね。
そんな中学生の頃からの熱を思い出させる武士をテーマにした本作品。
螺旋プロジェクトなので、戦国時代の武将たちが山族と海族に分かれる構図。
時代の結末は変わることがありませんが、
歴史の流れをなぞりながら、武将の内面にも触れられる機会にもなりました。
螺旋プロジェクトの共通キャラクターとして登場する
審判役やアイテムも出てくるファンタジーな世界が楽しめました。
戦国時代、どうしてそんなに戦をしないといけなかったのか?

本作では戦国時代の乱世の苦しみが印象的でした。
乱世となっていた戦国時代では
自分の家系を存続させるために、攻めてくる相手軍から自分達を守ったり、
縁を結んで、和睦を保とうとしたり、
家族が人質に取られたり、
裏切られたりと
本当に気の休まらない世の中ですよね。
戦国時代は
勝った武将だけがヒーローとして扱われがちですが
たくさんの武士が戦の無い世界を目指して苦しんでいたのかもしれませんね。
戦わなさすぎもダメになる?
何百年も戦いが続いた世の中から、ようやく平和の世の中になった江戸時代。
鎖国で外部からの刺激もない状態で、
250年経つと、固定観念、ダメな役人さん、平和ボケ、
現状維持バイアスでダメになっていくようです。
そこで起こった明治維新。
結局、戊辰戦争という形での決着でしたが。
坂本龍馬が目指していたように、武力ではない解決方法というエッセンスを
上手く自分なりに解釈させてもらうと
戦うというよりも、常に新しい刺激と挑戦にワクワクしていたいなと思いました。
現代で戦うことに疲れている自分へ

戦国時代を描くところでは
戦いの物語なだけあって、ずっと頭の中で鬨の声がなっていました。
ずっと心拍数が上がった感じで、
まったく、気の休まらない凄い時代ですね。
戦いながら泰平を願う気持ちは分かる気がします。
戦うのって疲れる。
ふと、自分の身の回りを眺めてみると
自分と合わないタイプっていますよね。
そんな時、イライラして冷静な判断が難しいまま応戦してしまいがちですが
そんなときは、自分とは逆のタイプ(山族または海族)と思い、
あまり争わないようにする癖をつけるのも良いかと思いました。
螺旋プロジェクト
井坂幸太郎さんの呼びかけで集った8作者による競作企画。
共通ルールを決めて、原始から未来までの歴史物語をいっせいに楽しめる企画。
(ルール)
①「海族」VS.「山族」の対立を描く
②共通のキャラクターを登場させる
③共通シーンや象徴モチーフを出す
共通ルールのもと、作者の織り成す個性が堪能できるのは贅沢ですね。
私も残りの作品を楽しみたいと思います。
(螺旋プロジェクト作品集)
・朝井リョウ:死にがいを求めて生きているの
・伊坂幸太郎:シーソーモンスター
・大森兄弟:ウナノハテノガタ
・薬丸岳:蒼色の大地
・吉田篤弘:天使も怪物も眠る夜
・天野純希:もののふの国
・乾ルカ:コイコワレ
・澤田瞳子:月人壮士